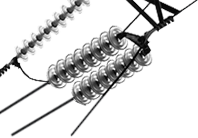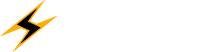事業を継続する上で、電気設備の安全性は決して軽視できない重要な要素です。特にキュービクル(高圧受電設備)は、企業や施設の電力供給を担う心臓部であり、その機能が停止すれば事業全体がストップしてしまいます。
しかし、すべての電気設備には耐用年数があり、それを超えて使用し続けることは大きなリスクを伴います。「まだ動いているから大丈夫」と考えていても、見えないところで劣化は進行しており、ある日突然トラブルが発生する可能性があります。
株式会社電気保安HIKARIは、電気設備の保守管理を専門とする企業として、特に老朽化した設備の安全管理に力を入れています。本記事では、耐用年数を超えたキュービクルが抱えるリスクと、当社が年次点検で実施する精密試験の具体的な内容について、詳しく解説していきます。
キュービクルの耐用年数と老朽化のリスク
キュービクルの法定耐用年数は一般的に15年とされていますが、これはあくまで減価償却上の年数です。実際の物理的な寿命はさまざまな要因によって異なります。主要な構成機器である変圧器、遮断器、開閉器などは、製造から15年から20年程度で交換やオーバーホールが推奨されています。
耐用年数を超えて使用し続けることで、どのようなリスクが生じるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
まず最も深刻なのが、絶縁性能の低下です。電気設備は経年とともに絶縁材料が劣化していきます。特に湿気の多い環境や温度変化の激しい場所では、この劣化が加速します。絶縁性能が低下すると、本来流れるべきではない場所に電気が漏れ出し、短絡事故や地絡事故の原因となります。
ある製造業のお客様の事例をご紹介します。そのお客様は20年以上同じキュービクルを使用されており、特に問題がないと考えておられました。しかし当社が点検を実施したところ、絶縁抵抗値が基準値を大きく下回っていることが判明しました。幸いにも事故が起きる前に発見できましたが、もし放置していれば火災につながる可能性もあった事例です。
次に問題となるのが、制御系機器の劣化です。キュービクル内には保護継電器と呼ばれる装置があり、異常を検知して電気を遮断する重要な役割を担っています。この機器が劣化すると、必要なときに動作しない、または不要なときに誤って動作してしまうことがあります。これは安全管理上、非常に危険な状態です。
さらに、部品の供給停止という問題もあります。古い設備は製造中止になっていることが多く、故障した際の部品調達が困難になります。緊急時に修理ができず、長期間の停電を余儀なくされるケースも実際に発生しています。
このようなリスクを未然に防ぐため、定期的な点検と適切な保守管理が不可欠なのです。
月次点検と年次点検の違い
電気設備の保安管理には、月次点検と年次点検という二つの柱があります。それぞれの役割と違いを理解することが、効果的な設備管理につながります。
月次点検は、その名の通り毎月実施する点検です。この点検は電気を停止せずに実施します。目視による確認、運転状態のチェック、計器類の読み取り、異常音や異常温度の確認などを行います。月次点検の目的は、日常的な異常の早期発見と、設備の運転状態の把握です。
一方、年次点検は年に1回、計画停電を伴って実施する精密な点検です。停電を伴うことで、月次点検では実施できない詳細な試験や測定が可能になります。これが年次点検の最大の特徴であり、設備の安全性を確保する上で欠かせないプロセスです。
お客様からよく「停電を伴う点検は業務に支障が出るので避けたい」というご相談をいただきます。お気持ちは十分に理解できます。しかし、年次点検で実施する精密試験は、設備の内部状態を正確に把握し、重大事故を未然に防ぐために必要不可欠なものです。
当社では、お客様の業務への影響を最小限に抑えるため、停電時間の短縮に努めています。事前に詳細な調査を行い、必要な試験項目を明確にし、効率的な作業計画を立てることで、停電時間を可能な限り短くしています。土日や夜間の実施にも対応しており、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応を心がけています。
年次点検で実施する精密試験の内容
ここからは、当社が年次点検で実施する主要な精密試験について、その目的と具体的な内容を詳しく解説していきます。
絶縁抵抗測定と接地抵抗測定
絶縁抵抗測定は、電気設備の安全性を確認する最も基本的な試験です。電気が設計された経路以外に漏れ出ていないかを確認します。測定には専用の絶縁抵抗計を使用し、機器や配線に一定の電圧をかけて抵抗値を測定します。
健全な設備であれば、絶縁抵抗値は非常に高い値を示します。しかし、絶縁材料が劣化していると、この値が低下します。基準値を下回っている場合、漏電や感電、火災のリスクが高まっていることを意味します。
接地抵抗測定は、万が一漏電が発生した際に、電気を安全に大地に逃がすための接地工事が適切に機能しているかを確認する試験です。接地抵抗が高すぎると、漏電時に電気が大地に逃げず、感電事故や設備損傷の原因となります。
これらの測定は法令で義務付けられており、基準値を満たさない場合は改善が必要です。当社では測定結果を詳細に記録し、経年変化を追跡することで、劣化の傾向を把握し、適切なタイミングでの改修をご提案しています。
絶縁耐力試験(耐圧試験)
絶縁耐力試験は、設備が設計基準を満たす高い電圧に耐えられるかを確認する試験です。通常の運転電圧よりも高い電圧を一定時間印加し、絶縁破壊が起きないことを確認します。
この試験は年次点検の中でも特に重要な位置づけにあります。なぜなら、実際に高い電圧をかけることで、絶縁材料の真の耐久力を評価できるからです。日常の運転では問題なく見えても、この試験で異常が見つかることは珍しくありません。
耐用年数を超えた設備では、絶縁材料が経年劣化により脆くなっています。雷サージや開閉サージなど、通常より高い電圧が瞬間的にかかった際、劣化した絶縁材料では破壊が起きる可能性があります。絶縁耐力試験は、このようなリスクを事前に評価するための重要な試験なのです。
試験は法令で定められた電圧を印加し、異常な電流の増加や絶縁破壊が発生しないことを確認します。もし異常が見つかった場合、その部分の修理や交換が必要となります。
保護継電器・遮断器動作試験
保護継電器と遮断器は、電気設備の安全を守る最後の砦です。過電流や地絡などの異常を検知すると、保護継電器が信号を発し、遮断器が電路を遮断します。この一連の動作が正確かつ迅速に行われることが、事故の拡大を防ぐ鍵となります。
しかし、これらの機器も経年劣化します。接点の摩耗や酸化、内部部品の劣化により、動作速度が遅くなったり、設定値がずれたりすることがあります。最悪の場合、まったく動作しないこともあります。
動作試験では、擬似的な異常信号を送り込み、保護継電器が規定時間内に正確に動作するか、それに連動して遮断器が確実に電路を遮断するかを確認します。タイムスイッチを使用して、動作時間を精密に測定します。
以前、ある商業施設で実施した動作試験で、遮断器の動作時間が基準値を大きく超えていることが判明しました。この状態では、事故発生時に十分な保護機能を発揮できません。すぐに遮断器の点検・調整を実施し、正常な動作を回復させることができました。もし点検を実施していなければ、実際の事故時に大きな被害が発生していた可能性があります。
このように、動作試験は設備の保護機能を確認する上で極めて重要な試験です。当社では、試験結果を詳細に記録し、前回の結果と比較することで、劣化の進行を把握しています。
無停電検査システムの活用
年次点検は停電を伴うため、24時間稼働が必須の施設や、停電による機会損失が大きいお客様にとっては大きな課題となります。当社では、この課題を解決するため、無停電検査システムの活用も可能な体制を整えています。
無停電検査システムとは、従来は停電が必要だった一部の精密測定や診断を、設備を停止せずに実施できる技術です。具体的には、活線状態での部分放電測定や赤外線サーモグラフィによる温度分布測定などがあります。
部分放電とは、絶縁材料の劣化部分で発生する微小な放電現象です。これは絶縁破壊の前兆であり、早期に発見することで重大事故を未然に防ぐことができます。従来は停電して測定する必要がありましたが、最新の測定機器を使用することで、活線状態でも検出が可能になりました。
赤外線サーモグラフィは、設備の温度分布を可視化する技術です。接続部の緩みや内部の異常は、温度上昇として現れます。負荷がかかっている状態、つまり活線状態でなければ検出できない異常もあり、無停電検査の重要なツールとなっています。
これらの無停電検査を月次点検時や計画停電前に実施することで、年次点検で実施すべき必須項目を絞り込み、停電時間を大幅に短縮することができます。あるデータセンターのお客様では、事前の無停電検査により、年次点検の停電時間を従来の半分以下に短縮することができました。
ただし、無停電検査ですべての試験が代替できるわけではありません。絶縁耐力試験や遮断器の動作試験など、停電を伴わなければ実施できない試験もあります。当社では、お客様の状況に応じて、無停電検査と停電を伴う精密試験を最適に組み合わせ、業務継続性と安全性の両立を実現しています。
設備更新とコスト削減の両立
耐用年数を超えた設備を抱えるお客様にとって、次の大きな課題は設備更新のコストです。安全確保のためには設備更新が必要だと分かっていても、その費用が大きな負担となり、判断を先送りしてしまうケースも少なくありません。
しかし、設備更新は単なるコストではなく、むしろコスト削減のチャンスと捉えることができます。当社では、電気保安の専門企業として、設備更新を経済的なメリットに変える提案を行っています。
最新の高効率機器は、旧型の機器と比較して電力損失が大幅に少なくなっています。特に変圧器は、20年前の機器と比較すると、最新機器では損失が半分以下になることもあります。これは電気料金の削減に直結します。
また、デマンド管理の最適化も重要です。デマンドとは、30分ごとの平均使用電力の最大値のことで、これが電気料金の基本料金を決定します。適切な管理により、ピーク電力を抑制することで、基本料金を削減できます。
以前、ある工場で設備更新を実施した際、高効率変圧器の導入とデマンド管理システムの設置により、年間の電気料金が約15パーセント削減されました。設備更新の投資は5年程度で回収できる見込みです。さらに、新しい設備は故障リスクが低く、保守コストも削減されています。
当社では、お客様の電力使用状況を詳細に分析し、最適な設備改修プランをご提案しています。省エネ診断を実施し、具体的な削減効果を数値でお示しすることで、設備更新の判断材料を提供しています。
また、補助金や助成金の活用もサポートしています。省エネルギー設備の導入には、国や自治体からの補助金が利用できる場合があります。申請手続きは複雑ですが、当社では申請書類の作成支援も行っており、お客様の負担を軽減しています。
当社の強みと地域密着のサポート体制
株式会社電気保安HIKARIの強みは、高品質なサービスを柔軟な料金プランで提供できることです。大手企業と比較しても遜色ない技術力を持ちながら、地域密着型の機動力により、きめ細かなサービスを実現しています。
当社のスタッフは全員が電気主任技術者などの専門資格を保有しており、豊富な実務経験を持っています。特に老朽化設備の診断や改修提案には自信があり、多くのお客様から信頼をいただいています。
料金体系は透明性を重視しており、すべてのサービス項目について分かりやすく説明しています。「他社と比較して料金が高い」「今の業者の対応に不満がある」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
東海地方を拠点とする地域密着型の体制により、緊急トラブルにも迅速に対応できます。異常が発生した場合、すぐに駆けつけて対応することで、施設運営への影響を最小限に抑えます。実際に、深夜に発生したトラブルにも1時間以内に現場に到着し、復旧作業を実施した実績があります。
また、乗り換えの際の手続きもすべてサポートいたします。現在の保安管理契約の解約手続き、電力会社への届出など、煩雑な手続きを当社が代行します。お客様は安心してお任せいただけます。
まとめ
キュービクルの耐用年数を超えた設備の安全管理は、事業継続に直結する重要な経営判断です。絶縁性能の低下や制御機器の劣化は、予期せぬ事故や火災のリスクを高めます。
当社が年次点検で実施する精密試験は、これらのリスクを正確に評価し、法令を遵守しながら安全な稼働を実現するための不可欠なプロセスです。絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、保護継電器・遮断器動作試験などの精密試験により、設備の状態を詳細に把握します。
また、無停電検査システムの活用により、業務継続性を保ちながら効果的な点検を実施することも可能です。さらに、設備更新をコスト削減のチャンスに変える提案を通じて、お客様の経営をサポートしています。
もし現在、今の料金に不満がある、または今の業者の対応に疑問を感じているなら、当社への乗り換えをご検討ください。専門資格者による高品質な対応と迅速なサポート体制で、お客様の電気設備の安全管理を万全にサポートいたします。
キュービクルの精密試験や安全管理についてのご相談は、お気軽にお寄せください。
メール:contact@d-hikari.co.jp(24時間365日受付)
電話:090-4140-8539
所在地:岐阜市加納本石町3-7 テイクオフビル3階